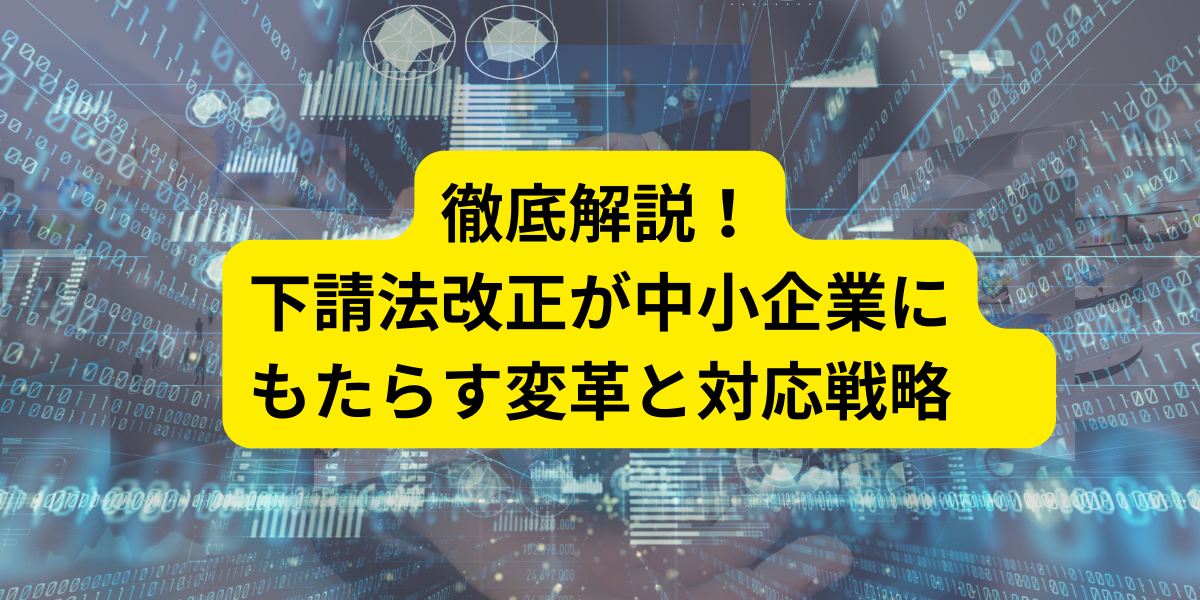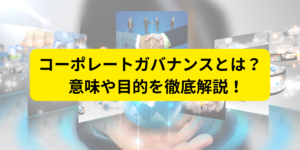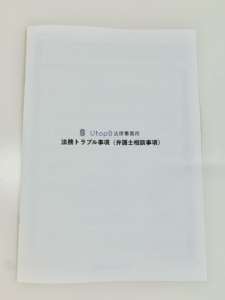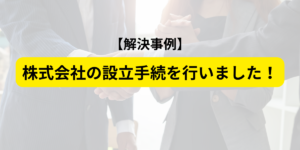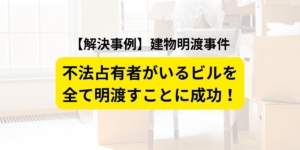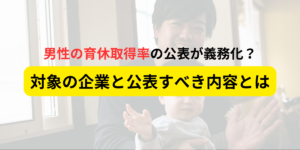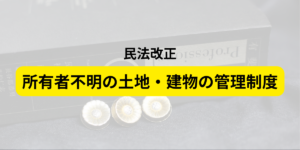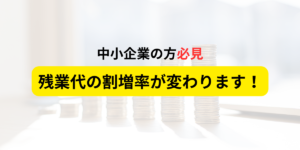下請法改正
日本の経済の屋台骨を支える中小企業の皆さん、そして日々下請事業者との取引に携わる親事業者の皆さんにとって、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます。)は、ビジネスの根幹に関わる重要な法律です。
この下請法が、近年の物価上昇等の経済状況や多様化するビジネスモデルに合わせて、大きく生まれ変わろうとしています。
特に、2026年1月1日に施行される改正法は、「下請法」から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)と名称も変更となり、内容も大きく変わるため、多くの企業に影響を及ぼすでしょう。
本記事では、この重要な下請法改正の背景から具体的な改正点、そして中小企業が今後どのように対応していくべきかについて、詳細な解説をお届けします。下請法に関する知識を深め、自社のビジネスをより強固なものにするための一助となれば幸いです。
※本記事では現行の略称の「下請法」を使用します。
下請法の目的と基本構造
下請法は、親事業者による下請事業者への不当な取引条件の押し付けや、下請代金の支払遅延・減額などを防止し、下請取引の公正を維持することを目的としています。
日本の産業構造では、親事業者が多数の下請事業者に部品やサービスを委託することが一般的であり、下請事業者は取引上弱い立場に置かれやすい現実があります。
こうした背景から、独占禁止法の補完法として1956年(昭和31年)に下請法が制定され、迅速かつ簡易な手続で親事業者と下請事業者との間の公正な取引を確保し、下請事業者の利益を守る仕組みが整えられました。
下請法の運用は公正取引委員会が所管し、違反行為の未然防止や是正のためのガイドライン・運用基準が定められています。
2016年(平成28年)には運用基準が大幅に改正され、違反行為事例が66事例から141事例に増加し、特に「買いたたき」や「減額」などの類型が明確化されました。
また、2022年(令和4年)には、労務費・原材料費・エネルギーコストの上昇分を価格に転嫁しない取引が「買いたたき」に該当することが明確化されるなど、時代の変化に応じた運用強化が続いています。
なぜ今、下請法が変わるのか?
制定から半世紀以上が経過し、以下のとおり経済構造や取引慣行は大きく変化したことから大幅な改正が行われました。
理由① デジタル化の進展と新たな取引形態
インターネットの普及、クラウドサービスの台頭、AI技術の発展など、デジタル化は私たちのビジネスを根底から変えました。これにより、従来の製造業における部品供給といった物理的な取引だけでなく、ソフトウェア開発、ウェブサイト制作、デジタルコンテンツの作成、フリーランスへの業務委託など、形のない「情報成果物」や「役務」に関する取引が飛躍的に増加しました。
しかし、これらの新しい取引形態に対する下請法の適用は、必ずしも明確ではありませんでした。
理由② サプライチェーンの複雑化
グローバル化が進み、企業間のサプライチェーンは一層複雑になりました。多段階の下請構造の中で、情報伝達の遅延や責任の所在の不明確化といった問題が生じやすくなり、下請事業者が不利益を被るケースも散見されました。
理由③ フリーランス・個人事業主の増加
働き方の多様化に伴い、フリーランスや個人事業主として働く人が増加しています。
彼らは企業から業務を請け負う形で生計を立てていますが、従来の法律では保護が手薄になるケースがありました。
特に、「フリーランス等保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の施行も相まって、フリーランスとの取引における公正性の確保が喫緊の課題となっています。
理由④ コスト上昇の転嫁問題
近年、原材料価格やエネルギーコスト、物流費の高騰、さらには最低賃金の上昇といった要因により、中小企業のコスト負担が増大しています。
しかし、そのコストを取引価格に適切に転嫁できないという問題が頻繁に指摘されてきました。
親事業者による「買いたたき」や、労務費などの交渉不調が下請事業者の経営を圧迫する状況を改善するため、より実効性のある法執行が求められていました。
理由⑤ 既存の下請法の課題
これまでの下請法は、その適用範囲や運用においていくつかの課題を抱えていました。
例えば、手形による支払いが依然として残っており、下請事業者の資金繰りを悪化させる要因となっていました。また、親事業者が下請事業者に不当な要求をした場合でも、下請事業者が報復を恐れて声を上げにくいという構造的な問題もありました。
これらの背景から、現代のビジネス環境に即し、より実効性の高い下請事業者保護を実現するため、下請法の改正が不可欠と判断されたのです。
何が変わるのか? 下請法改正の主要なポイント4点
2026年1月1日に施行される下請法改正は、多岐にわたる変更を含んでいます。
ここでは、特に重要なポイントを詳しく見ていきましょう。
改正ポイント① 適用範囲の明確化と拡大
これまで、下請法の適用範囲は主に製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つでした。(単純な販売契約などは含まれません。)今回の改正では、これらがより明確化されるとともに、事実上の適用範囲が拡大されることになります。
情報成果物作成委託・役務提供委託の明確化
情報成果物作成委託
ソフトウェア、ウェブサイト、デザイン、記事コンテンツ、ゲームなどのデジタル成果物の作成がこれに該当します。これまでも対象でしたが、その範囲がより明確になり、フリーランスや小規模なクリエイターが作成する多様なコンテンツも保護の対象となりやすくなります。
役務提供委託
運送、ビルメンテナンス、警備、情報処理、コンサルティングなど、サービス全般の提供が該当します。特に、IT分野におけるシステム運用保守やヘルプデスク業務なども含まれると解釈が広がり、これまで適用が曖昧だったサービス取引も保護対象として認識されるようになります。
適用対象の拡大(下請法逃れ対策)
現行の下請法では、親事業者と下請事業者の間の資本金基準によって適用が決まります。
例えば、製造委託の場合、親事業者の資本金が3億円超で下請事業者の資本金が3億円以下(または個人事業者)、親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で下請事業者の資本金が1千万円以下(または個人事業者)といった基準があります。
改正法ではこれに加え「従業員数」基準(製造委託等は300人、役務提供委託等は100人)を導入し、適用対象が拡大されました。
これにより、資本金が少なくても一定規模の事業を行う企業が下請法上の親事業者とみなされ、また資本金が一定額以下でも多くの従業員を抱える下請事業者が保護対象となりました。
改正ポイント② 親事業者の義務と責任の強化
下請法は、親事業者に課せられる義務を通じて下請事業者を保護する仕組みです。今回の改正では、これらの義務がさらに強化されます。
書面交付義務の徹底とデジタル化への対応
親事業者は、下請事業者に発注する際、直ちに下請代金の額、支払期日、支払方法、給付の内容などを記載した書面を交付する義務があります。この書面は「3条書面」と呼ばれます。
改正により、この書面交付義務は引き続き厳格に適用されますが、電磁的記録(電子メール、PDFファイル、クラウド上での共有など)による交付も正式に認められるようになりました。
これにより、取引の効率化が図れる一方で、下請事業者が確実に内容を確認し、保存できるような方法が求められます。親事業者には、電磁的交付を行う際に下請事業者の承諾を得るなどの配慮が必要です。
また、取引記録の作成・保存義務(2年間)も引き続き適用され、デジタルデータでの保存も認められます。
支払手段の適正化
これまで、手形による支払いは下請法上認められていましたが、割引困難な手形(支払期日までの期間が長い手形など)の交付は禁止されていました。今回の改正では、原則として手形による支払いは認められなくなりました。
さらに、電子記録債権やファクタリングを利用する場合でも、支払期日までに下請事業者が手数料を差し引かない「満額」の現金を受け取ることが困難な手段については、支払手段として認められなくなる方針です。これは、下請事業者の資金繰りを改善し、より確実な現金決済を促すための重要な変更点です。
コスト上昇分の協議と価格転嫁の促進
原材料費や労務費などのコストが上昇した場合、親事業者は下請事業者からの価格転嫁の要請に対して、適切な協議の場を設けることが一層強く求められます。
「買いたたき」の定義もより明確化され、一方的な価格据え置きや、コストに見合わない低い価格設定は、下請法違反のリスクが高まります。
公正取引委員会は、親事業者が価格転嫁を拒否する理由を下請事業者に書面等で明確に説明しない場合、買いたたきに該当すると推定される可能性を示唆しています。これは、親事業者に能動的な価格交渉の義務を課し、下請事業者のコスト負担を適切に反映するよう促すものです。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者が、自己の利益のために下請事業者に対し、協賛金や従業員の派遣、設備導入の強要など、不当な経済上の利益を提供させる行為は引き続き厳しく禁止されます。
特に、金型や治具の無償保管の要請など、これまで慣行として行われていた行為が改めて下請法違反として指導・勧告の対象となるケースが増えています。
改正ポイント③ 不当な行為への監視強化と罰則
公正取引委員会や中小企業庁による下請法違反行為への監視は一層強化されます。
報復措置の禁止の強化
下請事業者が、親事業者の下請法違反行為について公正取引委員会や中小企業庁に報告・申告した場合、親事業者はそのことを理由に、取引量の削減、取引停止、その他の不利益な取り扱いをすることは一切禁止されています。
改正では、この「報復措置の禁止」の申告先に、事業所管省庁(例:国土交通省の「トラックGメン」など)も追加されます。これにより、下請事業者がより安心して相談できる窓口が増え、報復を恐れることなく声を上げやすい環境が整備されます。
遅延利息の対象拡大
下請代金の支払いが遅延した場合、親事業者は遅延利息を支払う義務があります。改正の議論では、不当に減額された代金についても遅延利息の対象とするなど、下請事業者の不利益をより広範に補償する方向で検討が進められました。
指導・勧告・公表の積極化
公正取引委員会は、下請法違反行為に対して指導や勧告を積極的に行い、悪質なケースについては企業名を公表します。近年、勧告件数は増加傾向にあり、大手企業の子会社なども勧告の対象となる事例が報告されています。公表されることによる企業イメージへの影響は大きく、親事業者はこれまで以上に下請法遵守に努める必要があります。
改正ポイント④ 下請中小企業振興法との連携強化
下請法は取引の公正性を確保する「規制法」であるのに対し、下請中小企業振興法は、親事業者と下請事業者の協力関係を促進し、下請中小企業の振興を図るための「振興法」です。今回の改正では、両法の連携を強化し、下請事業者の経営基盤強化や生産性向上を支援する施策が、下請法の執行と並行して進められることが期待されます。
下請事業者(受注者)の皆さんへ
今回の下請法改正は、中小企業、特に下請事業者にとって大きな変化をもたらします。
下請事業者の皆さんは、今回の改正によってこれまで以上に保護が手厚くなることを理解し、自社の権利を適切に行使することが重要です。
下請事業者対応策① 契約内容の精査と交渉力の向上
親事業者から提示される契約書や発注書は、これまで以上に詳細に確認する習慣をつけましょう。特に、下請代金の額、支払期日、支払方法、給付の内容が明確に記載されているか、不明瞭な点はないかを確認してください。
今回の改正により、親事業者に明確な説明責任が課せられるため、疑問点があれば遠慮なく質問し、納得いくまで話し合うことが可能です。これは、下請事業者の交渉力を高めるチャンスでもあります。
不当な減額や買いたたき、無償での追加作業の要求などがあった場合は、下請法に違反する可能性を認識し、毅然とした態度で交渉しましょう。
下請事業者対応策② コスト上昇分の価格転嫁の申入れ
原材料費、エネルギーコスト、労務費などが上昇し、これまでの単価では採算が合わなくなる場合は、親事業者に対し、価格転嫁のための協議を積極的に申し入れましょう。「労務費転嫁指針」なども参考に、具体的なコスト上昇要因と転嫁を希望する金額を提示し、データに基づいて説明することが有効です。
親事業者が協議に応じない、または不当な理由で転嫁を拒否する場合は、下請法違反に該当する可能性も視野に入れ、後の証拠となるようやり取りの記録を残しておきましょう。
下請事業者対応策③ 支払方法の確認と早期現金化の意識
手形による支払いは原則禁止となり、電子記録債権等も実質的な満額現金化が難しい場合は認められなくなるため、現金・振込による支払いが主流となるでしょう。支払期日が60日以内であるかを確認し、資金繰りに問題がないか定期的にチェックしてください。
資金繰りに不安がある場合は、早期の現金化が可能なファクタリングなどのサービスも検討できますが、手数料が差し引かれない「満額」を受け取れるか、下請法に抵触しないかといった点に注意が必要です。
下請事業者対応策④ デジタル化への対応
書面交付のデジタル化が進むことで、電子契約やクラウドサービスでの情報共有が増えるでしょう。これらのツールを使いこなせるよう準備し、送られてくる情報が確実に確認・保存できる環境を整えましょう。
親事業者(発注者)の皆さんへ
親事業者の皆さんは、下請法改正によって、下請事業者との取引におけるコンプライアンス遵守の重要性が一層高まります。違反した場合の企業イメージへの悪影響や罰則のリスクを認識し、適切な対応が求められます。
親事業者対応策① 社内体制の再構築と教育の徹底
下請法改正の内容を正確に理解し、社内の発注プロセス、契約書のひな形、支払フローなどを全面的に見直しましょう。
特に、下請事業者との取引に直接関わる担当者(購買、開発、営業など)に対し、改正内容や下請法遵守の重要性に関する研修を定期的に実施し、意識を高めることが不可欠です。
安易な「買い叩き」や「一方的な減額」「無償での追加作業の要求」「金型等の無償保管要求」などが下請法違反となることを、全社的に周知徹底しましょう。
親事業者対応策② 明確な契約条件の提示と情報開示
下請事業者に対し、発注内容、下請代金、支払期日・方法などを、曖昧さなく、書面または電磁的記録で「直ちに」交付する義務を徹底してください。特に、デジタルデータでの交付を行う場合は、下請事業者が容易に確認・保存できる形式であること、そして事前に承諾を得ることを忘れないでください。
既存のテンプレート等の見直しも有効です。
「後から調整する」「とりあえず着手してほしい」といった不明確な発注は、トラブルの元となるだけでなく、下請法違反につながる可能性があります。
親事業者対応策③ コスト上昇分の協議と適正価格への見直し
下請事業者から価格転嫁の要請があった場合、真摯に協議に応じ、労務費などのコスト上昇分を考慮した適正な価格に見直す努力をしましょう。単に拒否するだけでなく、その理由を具体的に説明することが求められます。
価格交渉は、親事業者と下請事業者が対等なパートナーシップを築く上での重要な機会と捉え、長期的な関係性構築に資するよう努めましょう。一方的な価格決定は、サプライチェーン全体のレジリエンスを低下させ、最終的に自社の競争力も損なう可能性があります。
親事業者対応策④ 支払手段の変更と資金繰りへの配慮
手形による支払いを廃止し、原則として現金・振込による支払いに移行する準備を進めましょう。
電子記録債権やファクタリングを利用する場合も、下請事業者が満額の現金を支払期日までに受け取れる仕組みになっているか、慎重に確認する必要があります。下請事業者の資金繰りに配慮した、早期の支払いも積極的に検討しましょう。
親事業者対応策⑤ コンプライアンス体制の強化
下請法違反の疑いがある行為を早期に発見し、是正するための内部通報窓口の設置や、定期的な監査体制の構築なども有効です。公正取引委員会や中小企業庁からの指導や勧告があった場合には、速やかに改善計画を策定し、実行することが求められます。
具体的には対策としては、
- 下請法遵守マニュアルの作成・配布
- 定期的な研修の実施
- 内部監査体制の整備
- 内部通報制度の活用推進
があげられます。
親事業者対応策⑥ 下請事業者との良好な関係構築
パートナーシップの意識: 下請事業者を単なる「業者」としてではなく、自社の事業を支える重要な「パートナー」として認識し、長期的な協力関係を築くことを目指します。
生産計画や発注見込みなどの情報を適時に共有することで、下請事業者の生産計画や資金繰りの安定化を支援したり、 必要に応じて、親事業者が持つ技術や経営ノウハウを下請事業者に提供し、下請事業者全体の競争力向上に貢献することも、結果的に自社のサプライチェーン強化につながります。
下請法違反の具体的な事例とリスク
下請法違反は、企業のレピュテーションに深刻なダメージを与えるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。過去の具体的な違反事例や、企業が直面するリスクを理解しておくことは、下請法遵守のために非常に重要です。
よくある下請法違反の事例
違反事例① 下請代金の減額
親事業者が、発注後に一方的に下請代金を減額するケースです。
例えば、「最終顧客が安く購入したため、その分を下請代金から引く」「品質不良を理由に一方的に減額する(下請事業者に責任がない場合)」といった事例があります。
違反事例② 買いたたき
通常支払われる対価に比べて、著しく低い下請代金を不当に定めることです。例えば、市場価格や類似品の価格と比較して明らかに低い価格で発注したり、複数の下請事業者に競争させて不当に低い価格で契約させたりするケースが該当します。特に、近年のコスト上昇にもかかわらず、一方的に価格を据え置く行為も「買いたたき」に該当する可能性が高まっています。
違反事例③ 支払遅延
物品の受領日または役務の提供日から起算して60日以内に下請代金を支払わないことです。検査に時間を要する場合でも、60日以内に支払いを完了しないと違反となります。
違反事例④ 受領拒否
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品の受領を拒否したり、役務の提供を受け入れなかったりすることです。親事業者の生産計画の変更や、発注ミスなどが理由であっても、原則として受領拒否は認められません。
違反事例⑤ 有償支給原材料等の対価の早期決済
親事業者が下請事業者に原材料などを有償で支給し、その代金を下請代金から控除する際に、加工期間を考慮せず、下請代金の支払期日よりも早い時期に控除したり、加工に必要な量を超える原材料をまとめて買わせたりする行為です。
違反事例⑥ 不当な経済上の利益の提供要請
親事業者が、自己の利益のために、下請事業者に対し、協賛金、従業員の派遣、設備導入などの無償または低額での提供を要請する行為です。近年問題視されている金型や治具の無償保管の要請もこれに該当し、公正取引委員会による勧告事例が急増しています。
違反事例⑦ 不当な給付内容の変更・やり直し
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注後に一方的に給付の内容を変更したり、受領後に無償でやり直しをさせたりすることです。
違反事例⑧ 報復措置
下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁(改正後は事業所管省庁も)に親事業者の下請法違反を通報したことを理由に、取引を停止したり、取引量を減らしたりする行為です。
下請法違反のリスク
下請法に違反した場合、親事業者は以下のようなリスクに直面します。
親事業者リスク① 公正取引委員会による指導・勧告
違反行為が認められた場合、公正取引委員会は親事業者に対し、改善措置を講じるよう指導や勧告を行います。
勧告が行われた場合、原則として企業名や違反内容が公表されます。これは企業のレピュテーション(信用・評判)に甚大なダメージを与え、取引先からの信頼を失い、株価にも影響を及ぼす可能性があります。
親事業者リスク② 課徴金
特定の下請法違反行為(例:買いたたき、減額など)については、違反行為によって得た不当な利益相当額の課徴金が課される場合があります。
親事業者リスク③ 罰金
3条書面の交付義務違反や、取引記録の作成・保存義務違反などに対しては、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
親事業者リスク④ 損害賠償請求
下請法違反により下請事業者が損害を被った場合、下請事業者から親事業者に対して民事上の損害賠償請求が行われる可能性があります。
親事業者リスク⑤ ブランドイメージの悪化と採用への影響
企業イメージの悪化は、消費者からの評価を下げるだけでなく、優秀な人材の獲得にも悪影響を及ぼします。公正な取引を行わない企業として認識されると、従業員の士気低下にもつながりかねません。
下請法改正のその先へ~持続可能なサプライチェーンの構築~
今回の下請法改正は、単なる法規制の強化にとどまらず、日本経済全体のサプライチェーンの持続可能性を高めるための重要なステップです。
親事業者と下請事業者は、一方的な「強者」と「弱者」の関係ではなく、互いに協力し合い、共に成長する「パートナー」であるべきです。公正な取引慣行が確立されれば、下請事業者は安心して技術開発や設備投資を行い、親事業者は質の高い製品やサービスを安定的に調達できます。
特に、労務費の適切な転嫁は、中小企業の賃上げを促し、日本経済全体の活性化にも繋がります。また、下請事業者がイノベーションに取り組める環境が整うことで、サプライチェーン全体の競争力向上も期待できます。
「下請」という言葉自体が、もはや時代にそぐわないという声も上がり始め、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)という、より対等な関係を志向する名称への変更もされます。これは、従来の垂直的な支配関係から、水平的で協力的なパートナーシップへの意識改革が求められている証拠と言えるでしょう。
まとめ
2026年1月1日に施行される下請法改正は、日本のビジネス環境における「公正な取引」のあり方を大きく変えるものです。特に、デジタル化の進展やフリーランスの増加、そしてコスト高騰といった現代の課題に対応するため、親事業者の義務は強化され、下請事業者の保護は一層手厚くなります。
親事業者は、書面交付の徹底、支払手段の適正化、コスト上昇分の協議と価格転嫁への積極的な対応、そして社内コンプライアンス体制の再構築が急務です。
下請事業者は、改正法の内容を理解し、自身の権利を主張すること、不当な要求には毅然と対応すること、そして困った時にはためらわずに公的機関や専門家を頼ることが重要です。
今回の下請法改正は、一時的な対応で終わるものではありません。持続可能で強靭なサプライチェーンを構築するためには、親事業者と下請事業者が互いを尊重し、長期的な視点に立って協力していくことが不可欠です。
このブログ記事が、皆さんのビジネスにおける下請法改正への理解を深め、適切な対応を講じるための一助となれば幸いです。
下請法関係のご相談は、是非、Utops法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
当事務所の弁護士は、経済産業省や上場企業での豊富な勤務・役員経験を活かし、企業内での法的問題に精通しています。
経営者様や担当者様が直面する複雑な法的課題に対して、迅速かつ的確な対応が可能で、企業の成長を支えるサポートをお約束します。